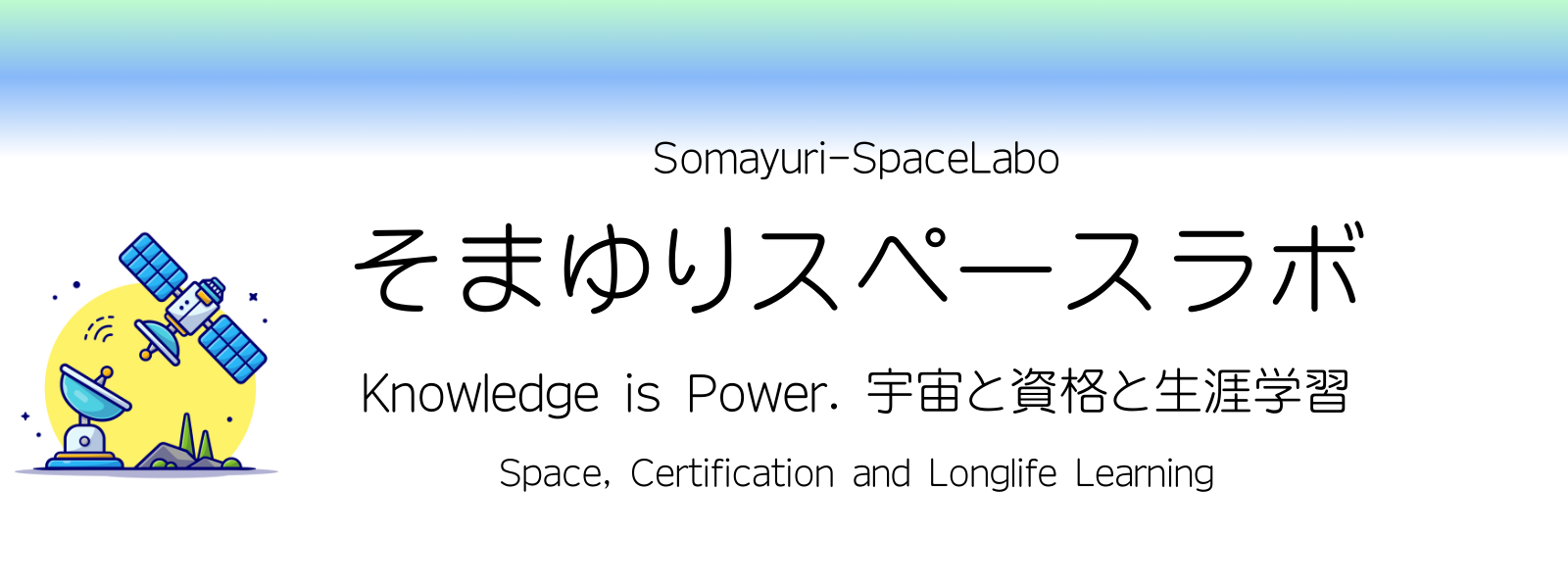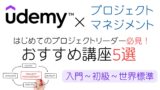PMP(Project Management Professional)資格の受験を検討されている方、既に勉強を始めている方、またはPMPを実務に適用しようとしている方の中には、果たしてPMP資格は意味があるのだろうか、もしかしたら意味ないのでは?と疑問を持たれている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、PMPが意味ないと感じる理由を言語化し解説します。
PMPを受験するか否か、またPMP資格を理解する上でのひとつの材料としてご活用下さい。
この記事を読んで頂きたい対象の方
- PMP資格の取得を検討中の方、既に勉強中の方
- PMPを実務に適用しようとしている方
PMP試験のメリット・デメリット、難易度・合格率・勉強時間については、以下の記事をご参考下さい。
■なぜ意味ないと感じるのか
著者も経験がありますが、PMPを学習していると、ふと以下のような疑問を持つことがあります。
せっかく勉強していても意義を感じることが出来ないとモチベーションを維持するのも難しく、途中で諦めることにも繋がりかねません。
ではなぜこのような疑問を持つのか、その理由は大きく4つあります。
これらはPMPを学習する上での前提事項と言えるもので、PMPを学習する方は理解しておく必要があります。
順番に解説していきます。
■PMPは意味がないと感じる4つの理由

【理由1】PMBOKはあくまでもプロジェクトマネジメントの標準ガイドライン
PMP資格の学習は、PMBOK(Project Management Body of Knowledge)の学習に他なりませんが、PMBOKはあくまでもプロジェクトマネジメントの”標準ガイドライン”であるということを理解していないと、学習していても”腑に落ちない”かもしれません。
従って、プロジェクトをこのように進めていけば正解である、という“答え”を示してくれるものではありません。
また、プロジェクトをこのように進めていかなければならない、という“ルール”でもない、ということです。
まずは、この前提を理解しておく必要があります。
【理由2】PMPの内容と日々の実務とのギャップを埋める作業が必要
PMPの内容が日々の実務と組織的、文化的にかけ離れていて、実務に使えそうな技法が少ないと感じる方もいるかと思います。
PMO(Project Management Office)がご自身が所属する会社には存在しない場合など、組織の成熟度も企業によって異なります。
また、任命されるプロジェクトの規模や役割、特性も様々かと思います。
このようにPMPは標準ガイドラインであるが故に、各々が置かれてる状況とは大なり小なりギャップが生じます。
このギャップを埋める作業が“テーラリング”になります。
プロジェクトの立上げから終結までご自身が所属する会社の規則や手続きに則りつつ、適用するプロジェクトの特性に合わせて、標準ガイドラインの内容を最適なものに変更(テーラリング)する必要があります。
これが標準ガイドラインとご自身が置かれた環境とのギャップを埋める作業になります。
PMPの学習をする上で、またはPMPを実務に適用する上でテーラリングという重要なコンセプトを理解しきれていないと、学習内容が腑に落ちない、使えない知識、という思い込みに陥ってしまうかもしれません。
【理由3】PMPは汎用的な知識体系であり、特定の産業や分野に特化してるわけではない
PMPは汎用的な知識体系であり、特定の産業や分野に特化してるわけではなく、あくまでもプロジェクトマネジメントの優れた枠組みを学ぶものです。
実際のプロジェクトでは、この汎用的な知識に加えて、各産業に特化した専門知識や経験が必要となります。
これらの知識・経験を有している個人・グループを「専門家」と呼びます。
この専門家とプロジェクトマネージャーの実務範疇を混同してしまうと、PMPの学習内容が”腑に落ちない”かもしれません。
著者は、人工衛星の運用設計エンジニアですので「人工衛星の運用設計」に関する「専門家」です。
その一方で「人工衛星の運用設計」プロジェクトを推進していくプロジェクトマネージャーでもあります。
専門家として、成果物の設計・製造・試験などの実務を行う一方で、担当するプロジェクトのスコープ・スケジュール・コスト等の各プロジェクトマネジメント知識エリアに関してマネジメントを行っており、このマネジメント業務に対して、PMPで学習したプロジェクトマネジメント標準プロセスをテーラリングして適用しています。
おそらくこの記事を読まれている方は、「プロジェクトマネジメント専任」という方は多くなく、なんらかの分野の「専門家」でありながら、プロジェクトマネジメント業務を兼任されている方が多いのではないでしょうか。
専門家とプロジェクトマネージャの実務範囲を明確に分離して考えると、PMPの適用範囲を見失わずにすむでしょう。
【理由4】”どのように実行すればよいか”までは具体的に示されていない。
実務において、PMPで学習した具体的な技法を試したいと考えたとしても、“どのように実行すればよいか”までは、PMBOKには具体的に示されていないことがほとんどです。
例えば、スコープを定義するための技法(要求事項分析、プロダクトブレークダウン、価値分析など)を実務で試そうとした場合、PMP資格では、技法の名称や概要をさらっと学習することはできても、技法の詳細内容や使い方などは具体的に示されていません。
なぜならば、技法はそれだけで一冊の本になるほど内容が深く、また分野ごとの特性によって使用されるべき方法論やツールが異なるからです。
適用するには、別途、方法論を学習する必要が生じます。
つまり、PMPを学習しても、マネジメントに有効な技法を知ることができますが”使い方”を知ることは出来ないという辺りが「意味がない」と感じさせる一因となり得ます。
■まとめ
いかがでしたでしょうか。
以下、PMP試験が意味ないと感じる理由をまとめておきます。
【PMP資格が意味ないと感じる4つの理由】
- PMBOKはあくまでもプロジェクトマネジメントの標準ガイドライン
- PMPの内容と日々の実務とのギャップを埋める作業が必要
- PMPは汎用的な知識体系であり、特定の産業や分野に特化してるわけではない
- “どのように実行すればよいか”までは具体的に示されていない
【結論】
結論としては、PMPを学習する意味は大いにありますが、PMPを学習する上でこれらの前提事項を理解しておかないと学習内容が”腑に落ちない”ということになり得ますので、しっかりと理解することが肝要です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
PMPは著者が取得してきた資格の中で仕事上最も役に立つ資格のひとつです。
少しでも皆さまのお役に立てたなら幸いです。